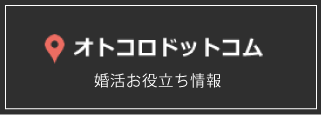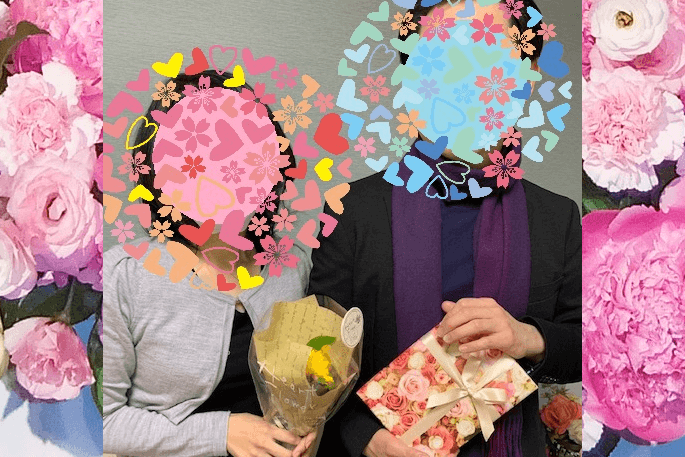-

結婚が現実味を帯びてくると、住まい選びや両家の顔合わせ、式の準備など、考えることが一気に増えていきます。
そんな中で、「結婚後の姓をどうするか」が問題になるカップルもいます。
最近は特に20代の皆さんの中で「女性が自分の姓を名乗りたい」「男性はどちらでもいいと考えている」というケースが増えていて、真剣交際中で成婚が直前となったカップルから相談を受けることも多くなりました。
それでも現実には、夫の姓を選ぶ夫婦が圧倒的多数を占めており、特に女性側が「本当は自分の姓を選びたかったのに……」とモヤモヤを抱えたまま改姓に踏み切ることが少なくありません。
この記事では、戸籍制度の基本から、夫の姓・妻の姓を選ぶそれぞれのメリット・デメリット、話し合いのステップをわかりやすくまとめています。
結婚を前に、「姓の選び方」を考える参考にしていただければ幸いです。
目次
結婚すると、姓はどうなる?戸籍制度の基本をおさらい
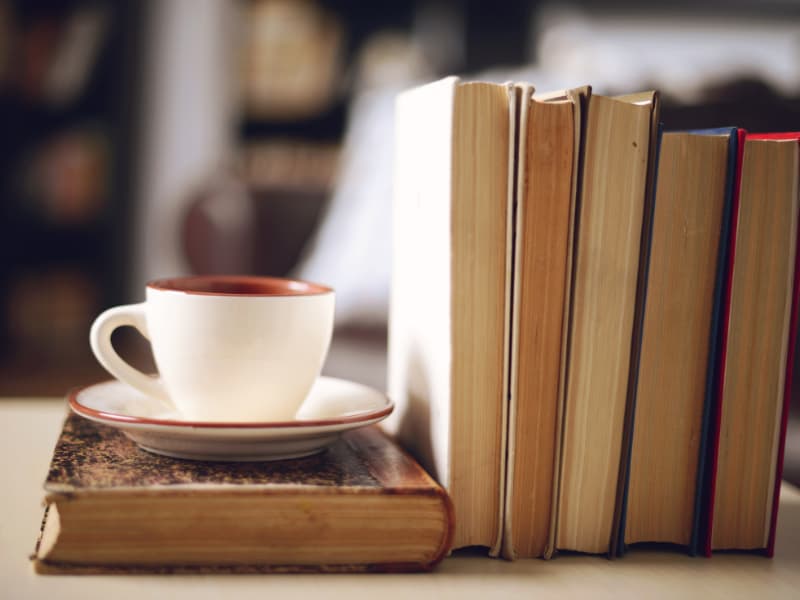
戸籍制度を詳しく調べてみて
「姓をどうするか」という問題に直面した時に、検討材料に必要なのが戸籍制度の基礎知識です。
意外と知られていない制度の基本を、まずは知っておきましょう。
夫婦同姓が原則、別姓は認められていない
日本では、民法第750条により「夫婦は同じ姓を名乗る」ことが法律で定められています。
いわゆる“選択的夫婦別姓”は現在の法律制度では認められていないため、婚姻届を提出する時に夫の姓・妻の姓のいずれかを選び、同じ戸籍に入る必要があります。
📘 民法750条より
「夫婦は、婚姻の際に定めるところにより、夫または妻の氏を称する」
▶ 結婚時に夫・妻どちらかの姓を選ぶ必要があり、同姓が原則です。「夫の姓」「妻の姓」どちらでも自由に選んでいい
「夫の姓」と「妻の姓」の、どちらを選んでも法的にはまったく問題ありません。
しかし、現実には約9割以上の夫婦が「夫の姓」を選択しているというのが実情です。
💡実際にはどうなの?
夫の姓を選ぶカップルが圧倒的に多く、法務省の統計(2022年)によると、結婚した夫婦のうち94.4%が「夫の姓」を選択しており、「妻の姓」はわずか5.6%にとどまります。姓を変えても旧姓を使える「通称使用制度」
女性側が仕事や資格、社会的な実績の関係で旧姓を使いたい場合には、男性の姓に変えたとしても旧姓を継続利用することもできます。
これは「通称使用」と呼ばれる運用の仕方で、特に女性の社会的活動やキャリア維持などを目的とする方々に活用されているケースが増えています。
💼 たとえばこんな場面で旧姓を使えることがあります:
・職場の名刺やメールアドレス
・医療や教育など、名前で信用が紐づく専門職
・行政文書(住民票の備考欄)での記載 もっと詳しく!通称使用を行うにはどうすればいいの?通称使用は「自分の意思で名乗るだけ」ではなく、勤務先や公的機関に対して一定の手続きや実績が必要と言われています。
もっと詳しく!通称使用を行うにはどうすればいいの?通称使用は「自分の意思で名乗るだけ」ではなく、勤務先や公的機関に対して一定の手続きや実績が必要と言われています。 カウンセラー
カウンセラー●行政機関の場合
住民票やマイナンバーの情報に旧姓を併記することが可能ですが、婚姻前の氏が記載された戸籍謄本などを提出する必要があります。●会社の場合
名刺やメール表示を旧姓の氏名で表示する場合は、所属する会社の社内規定に沿って申請し、正式な段取りで社内に登録しておく必要があります。●銀行・保険等の契約
原則は戸籍上の姓でしか契約できませんが、一定の条件に沿うことができれば、金融機関によっては旧姓を併記できる可能性もあります。💡注意しておきたいこと
通称使用は法律上の「本名」ではないため、パスポートや運転免許証、各種契約書では戸籍名での手続きが基本です。 状況によっては、旧姓と本名の使い分けに混乱を生むこともあるため、使用範囲と管理には注意が必要です。夫の姓・妻の姓、それぞれを選んだ場合のメリット・デメリット

メリットとデメリットを紹介します
「どちらの姓にするか」という選択は、単に“名前が変わる”という話にとどまらず、家族関係・人生観・社会的立場など、さまざまな背景が関わるとても繊細なテーマです。
夫の姓・妻の姓を選んだ場合の代表的なメリット・デメリットを整理しておきますね。
夫の姓を選んだ場合(多数派)
👨 夫の姓を選んだ場合の特徴✅ メリット
- 🔸 社会的慣習に沿っているので、周囲からの理解を得やすい
- 🔸 手続きやいろいろな書類の対応がスムーズ
- 🔸 親族との関係が円滑に進みやすい
⚠ デメリット
- 🔸 女性側が名義変更など多くの手続きを負担することに
- 🔸 キャリア・実績の一貫性が失われることがある
- 🔸 女性の心に「本当は変えたくなかった」と後悔が残ることも
妻の姓を選んだ場合(少数派)
👩 妻の姓を選んだ場合の特徴✅ メリット
- 🔸 女性のキャリアや実績を維持しやすい
- 🔸 対等に話し合って決めた実感が得られる
- 🔸 柔軟な家族観を築くきっかけになる
⚠ デメリット
- 🔸 男性が“婿入りした”と誤解されやすい
- 🔸 親族の反応に気を遣う場面がある
- 🔸 役所や手続きで驚かれるケースが多い
姓をどう選ぶ?話し合いのステップと心得

話し合う心得と大事なポイント
「どちらの姓にするか」をテーマに掲げ、結婚に向けて話し合おうと提案するのは主に女性です。
男性からあえて姓の選択について確認しあおうとすることはほとんどなく、男性の姓を選ぶのがまだまだ当たり前となっている社会です。
とはいえ、納得の選択ができないままで結婚してしまったら、いつか後悔するときがくる…これは絶対に避けたいですね。
それくらい大事なテーマだと思いますので、姓をどうするか迷う気持ちがあるのなら、見過ごしたり先送りせずに話し合ってみてください。
話し合い前に心得ておくべきこと
話し合いのなかで、お互いに今まで気づかなかった価値観や思いが浮かび上がってくることもあります。
結婚相談所で交際中の女性が、「妻側の姓にしてほしい」という要望を出した途端に、男性が交際を終了してくることも覚悟しなければなりません。
二人で納得して決めたとしても、特に男性が女性の姓に替えることは一般的ではないので、男性側の両親が手放しで喜んでくれることはなく、結婚そのものを反対されてしまうケースもありました。
そうした実際のケースがあることも想定した上で、話し合いに入りましょう。
6つのステップで考える「納得できる」選ぶ方
「どちらの姓にするか」を話し合うとき、感情論や場の雰囲気だけで決めてしまうと、あとから後悔や不満が生まれてしまうこともあります。
だからこそ、ふたりで納得しながら進めるための話し合いには、いくつかの大切なステップがあります。
一方的にどちらかが折れるのではなく、将来を見据えながら対等に考え、理解を深めていく——そのプロセスが「結婚後の姓」を前向きに選ぶための大きな鍵になります。
ここでは、話し合いの進め方を6つのステップに整理してご紹介します。
🔍 姓をどうするか?話し合いの進め方・6つのステップ- 1.お互いの本音を出し合う
「本当はどうしたいか」「なぜそう思うのか」を遠慮せずに話す - 2.手続き・周囲への影響も具体的に考える
親・親戚・仕事上の名義など、現実的な部分もリストアップ - 3.特に男性側の家族の考えをヒアリングする
勝手に決めて結婚を反対されないよう親の考えを確認しておく - 4.子どものことも含めた未来視点で考える
名字をどう残したいか、学校や家庭内での影響も想定する - 5.通称使用や、別姓希望のスタンスも確認
柔軟な制度活用や将来の法改正への考えも共有しておく - 6.「決める」よりも「納得する」ことを重視する
ふたりが納得して前向きに決められたかどうかが大切
💡結婚前に話し合うべき価値観として「実家との距離感」も大切なテーマです
まとめ|どちらの姓にするか、ふたりの在り方を映す選択

丁寧に話し合っていく努力を!
結婚後の姓をどうするかは、夫婦としてどんな人生を歩んでいくかを象徴する、非常に大切なテーマです。
法的にはどちらの姓でも構わないにもかかわらず、社会的な慣習や周囲の目を気にして、「なんとなく」夫の姓に落ち着いてしまう…そんなカップルは今も少なくありません。
本来はふたりで自由に決めていいことですが、氏名は、日々の生活や人間関係、仕事、家族関係など、あらゆる場面に影響を与えます。
変える側にだけ負担が集中したり、「仕方なかった」という感情が残ったままだと、心にわだかまりが積もってしまいますので、相手の考えや価値観に対して、思いやりを持った姿勢で一緒に考える機会をもってみてくださいね。
🔖 結婚後の「姓の選び方」、こんな悩みにも対応します。
「名字を変えるのが不安」「親にどう説明すればいい?」
そんな気持ちの整理や、制度の確認も含めて相談できるのがブライズデザイン。
婚活のプロに気軽にLINEで相談してみませんか? -